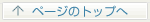授業に対する質問・コメントQeustion and Comments
第1回授業1st
| Question / Comments | Answer |
Q. GPS、ナヴィゲーションの話について |
A. 地球観測(リモートセンシング:リモセン)衛星は、軍事目的であれば以前は偵察衛星(スパイ衛星)と呼ばれることもありましたが、現在では民生目的や商業目的で製造・運用されるリモセン衛星があり、そのデータも災害対策や農地管理、漁業など幅広い分野で利用されています。ご指摘のとおり、観測される側の国「被探査国」の主権侵害の問題は1980年代から議論されてきました。 ただ、リモセンのデータは写真と異なり、衛星から得られるデータそのものでは地表の状況を識別することはできません。解像度を上げるにはデータの「処理」や「加工」が必要です。 国際宇宙法では国連リモートセンシング原則というルールがあり、データを「一次データ」「処理済みデータ」「解析された情報」とに分けて規制の内容を調整しています。その目的は、被探査国の国家安全保障に影響を及ばさないことです。分解能が高い画像の売却は外交問題を引き起こすことも考えられますので、高分解能のリモセン衛星の所有国は、国内法により地球観測ビジネスを規制しています(米国・カナダ・ドイツなど)。これは政府による制限「シャッター・コントロール」と呼ばれるもので、Google社といった民間企業の活動は規制の対象となっています。 |
C. 宇宙民間利用・商業発展(宇宙旅行など)の |
A. リクエストありがとうございます!宇宙法の講義第6回・第7回で扱うようにしますね。 |
Q. 月の土地の権利書のお話で |
A. 今日は宇宙空間および月など天体には国家主権は及ばないというお話をさせていただきました。宇宙条約は「国家の宇宙活動」に関する権利や義務を規定していますが、そのなかに「国家責任」(State Responsibility)に関する条項があります(第6条)。これは自国民の宇宙活動(宇宙ビジネスなど)が、条約上の国際義務に違反しないよう、国家は民間企業の活動を「継続的に監督」しなくてはならないと義務づけるものです。月の土地に関していいますと、米国が所有できない土地を米国の民間企業が所有・売買することはできません。このため、当該権利書は物権を伴わない書面です。このため本来なら米国が当該企業に対し何かしら規制や勧告をすべきと説明させていただきました。第4回の講義で詳しくご説明しますね。 |
Q. COPUOSにおいてはコンセンサス方式で |
A. COPUOSが意思決定プロセスにコンセンサス方式を採用したのは1962年でして、国連ではCOPUOSが最初に採用し、その後はWTO、OECD、IMFも採用しています。(参照元:A. Soucek, Space Law Essentials, vol. 1, Linde Verlag, 2015, p.13) 採用の経緯を示す国連決議の文書(A/AC.105/PV.2, 19 March 1962)が国連のHP上で見つからないのですが、軍縮に注力していた1960年代の国連では、反対を唱える国がなくなるまで交渉し、すべての関係当事国が賛成することで、有効性の高い条約の策定を目指していたのかと思います。 宇宙ならではの特異性という点では、まず宇宙技術が民生目的でも軍事目的でも利用が可能という「デュアルユース」の性質である点、また、宇宙活動から得られる「利益」が国家によって異なる点、外交上の配慮(例:欧米サイドか中露サイドか)など、また、COPUOS加盟国の増加(95か国と42の国際機関:2021年時点)といった複数の要因が考えられ、このためにコンセンサスに至ることが大変難しくなっている状況です。 |
第2回授業2nd
| Question / Comments | Answer |
Q. スライド17枚目の「5つの自由」について |
A. 第3の自由と第4の自由は、自国と相手国との間で貨客の積み込み、積み下ろしを行う自由でしたね。自国から運輸が第3の自由、自国への運輸が第4の自由になり、この2つの自由をまとめて「運輸権(traffic right)」といいます。国際航空運送協定(International Air Transport Agreement)第1条が定めているのですが、起草過程をみないと区別した背景まで分かりませんでした。今後調べてみて、何かわかりましたら講義で共有させていただきますね。 |
C. 今回の講義のきっかけに初めて、 |
A. 講義をもとに積極的に調べてくださり、また、それを共有してくださりありがとうございます!ADIZに領空主権がない一方で、排他的経済水域では沿岸国は天然資源に対して「主権的権利」を有しますよね。しかしEEZ上には「上空飛行の自由」もあり・・なんとも複雑で、私もADIZに関心が出てきました! |
Q. スライド19枚目において、軍事目的で |
A. まず民間航空機を本来の目的以外に使用した場合(軍事目的など)、シカゴ条約4条違反になりますが、すぐに要撃が可能ということにはなりません。そして要撃の際、武器の使用は禁止されると講義でお話しました(シカゴ条約第3条の2)。非武装の民間航空機による領空侵犯の場合、無線通信を試みた後に翼を振り航空等を点滅させて警告・着陸要求を行い、従わない場合には進路妨害なとで対処しますが、その際にも武器の使用は原則として禁止されています。(黒崎将広ほか『防衛実務国際法』弘文堂、2021年、94-195頁)。上述の3条の2が追加された際の経緯(配布資料10頁)を見ますと、要撃を可能とする条件がかなり厳格化されていると考えられます。 |